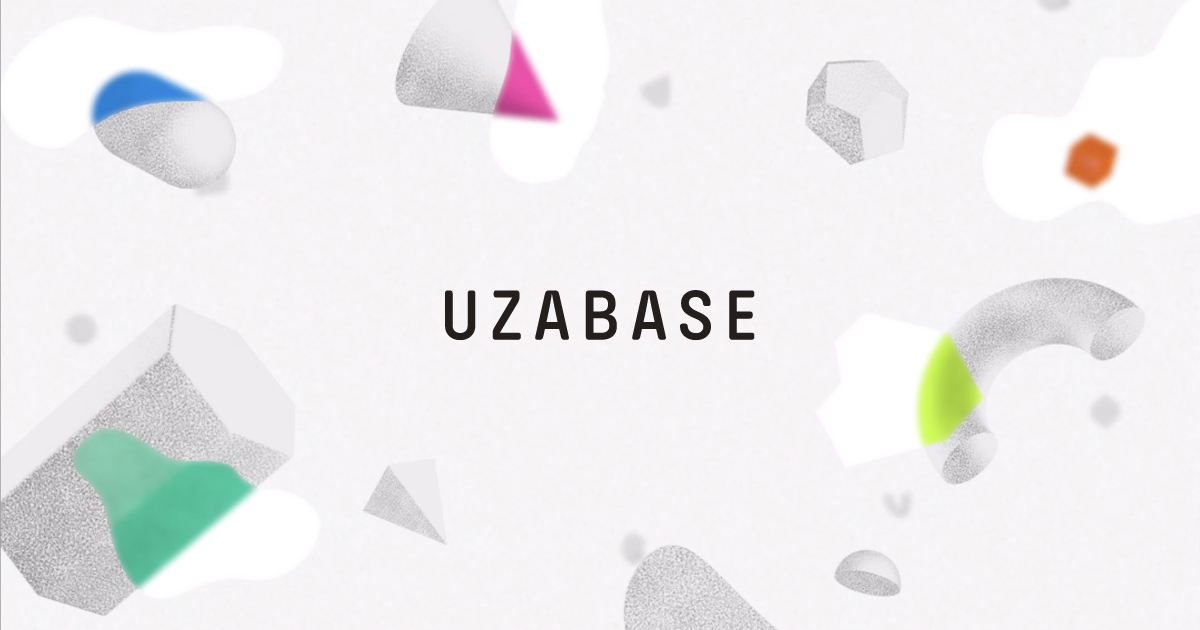理念とは?(ミッション・パーパス∕ビジョン∕バリュー)

この記事では、企業経営について最も重要な理念とは何かを説明しています。経営に迷ったらどこを拠り所とすればよいのか、今理念を策定したり変更したりしたほうが良いのか悩んでいる⽅にとって明確な解答になるはずです。
理念とは
結論からいうと、理念とは「会社や経営に関するすべての根幹となる考え⽅や拠り所」のことで、存在意義、⽬指す姿、価値観などをまとめたものです。
もちろん様々な考え⽅がありますが、過去の経験や良い企業経営を⾒てきた観点からはこのように考えればほぼ間違いありません。具体的にまとめると以下3点といえます。英⽂で⾒ると判りやすいと思うので英訳も添えています。
- ミッション・パーパス(存在意義 ー Why We Exit)
なぜ、⾃社が存在するのか? - ビジョン(⽬指す姿 ー Where We Go)
存在意義を実現した状態はどうなっているのか? - バリュー(価値観 ー What We Believe)
どのような考え⽅で⽬指す姿を実現するのか?
そして、これら以外はすべてアウトソーシング(外注)ができるためです。⾝近な例でも、街の飲⾷店は「飲⾷」を提供しているという点では皆同じといえますが、なぜやっているのか、どのようになりたいのか、どのような考え⽅でやっているのかは各店違うわけで、だからこそ価値があるわけです。
ドラッカーも以下のように⾔っています。
ネクスト・ソサエティにおける企業とその他の組織の最⼤の課題は、社会的な正当性の確⽴である。すなわち、価値(バリュー)、使命(ミッション)、ビジョンの確⽴である。他のものは、すべてアウトソーシングの対象となりうる。
ネクスト・ソサエティ | PFドラッカー(著), 上⽥ 惇⽣(翻訳)
では、それぞれ具体的に⾒ていきましょう。
ミッション(Mission)・パーパス(Purpose)
ミッションの重要性
なぜミッションやパーパスが重要かというと、会社が存在する理由がわからなければ事業や経営を⾏う意味、やりがいなどがわからなくなってしまうからです。
当然、会社経営は良いことばかりではありませんので、このような想いがなければ「他社がいれば良いのでは?」と頑張れなくなってしまいますし、⼈材を採⽤するにも⾃社で働いてもらう理由を説明できなくなってしまいます。
特に⽇本では、⼤きな移⺠政策の変更がない限りもう⼈⼝が増加することはありませんので、国家の成⻑や⾼度成⻑とともに会社を成⻑させることは不可能ですし、そこに⼤きな意味や意義はありません。例えばコンビニの近くにコンビニをつくったり、居酒屋のとなりに似たような居酒屋をつくったり、他社がつくった製品を真似た製品をつくったりして、いったい誰が幸せになるのでしょうか?
もしあるとすれば、そこに「やる意味」がある場合だけです。例えば「もっと皆が健康になってほしいから⾃然⾷レストランを出す」などです。だからこそ企業経営において最初に考えなければならないのはこのミッション・パーパスになります。
例えば、テスラさんのミッションは” Accelerating the World’s Transition to SustainableEnergy(世界の持続可能なエネルギーへの移⾏を加速する)” であり、⾞・モビリティをつくりたいわけではなく、⾞はあくまで⼿段であるわけです。
だから⾃動⾞関連事業とは違うソーラーパネル事業を⾏っても、それは理念に即した活動といえるわけです(もちろん事業シナジーはありますが)。
経営には賛否両論あれど、この⾼い存在意義が優秀⼈材や顧客とのつながりの端緒となっていることは間違いありません。
また、サイモン・シネック⽒のゴールデンサークル理論(以下TEDの動画「How Great Leaders Inspire Action 優れたリーダーはどうやって⾏動を促すのか」で提唱)にもあるように、WHY(ミッション・パーパス)から始めることが⼤切といえます。
理論詳細は以下動画をご覧頂ければと思いますが、例えばある糖質カット製品も、ただその糖質が低いこと=WHAT(何をつくったか)を伝えるよりも「糖尿病で苦しんでいる⼈が少しでも安らげるように」というWHYを伝えたほうが響きますし、本来そうあるべきではないでしょうか。
【TED】優れたリーダーはどうやって⾏動を促すか/サイモン・シネック (⽇本語字幕)
ミッションとパーパスの違い
ミッションとパーパスの違いについてよく質問されたり、議論されたりしますが、結論としては「想いが同じなら⾔い⽅はどちらでも良い」と考えます。
よくある整理としては以下の通りです。もちろんこの形で整理しても全く問題ありません。
- パーパス=WHY
- ビジョン=WHERE
- バリュー=HOW
- ミッション=WHAT(何をするのか?=経営戦略)
ミッションは何をするかで、パーパスは志なのだというコンサルタントもいますが、最上位概念が「WHY」であり、それを何と呼ぶかはただの翻訳遊びで「そのWHYが何か?」のほうがよほど⼤切です。
「他社と同じビジネスを同じようにただやっているだけなのに、⾔い⽅をパーパスに変える」などの例をよく⾒ますが、いったいその⽂章が誰に刺さっていて、誰のためになっているのかと周囲は冷めた⽬で⾒ているものです。なぜなら、本来改⾰すべきなのは⾔い⽅ではなくビジネスそのものだからです。社員からすれば「この⼋⽅塞がりで未来が⾒えない状態をなんとかしてくれ。まずは残業をなんとかしてくれ」と思っているはずです(何もしない社員も問題ですが)。
つまりクラウドと呼ぼうがオンラインサービスと呼ぼうが⽬的が達成できれば良いのと同じことで、流⾏り⾔葉などに惑わされず、⾃信をもって経営していけば良いのです。
※本記事では、ミッション≒パーパスでほぼ同意と捉え、混乱しないように併記しており、WHATは経営戦略であり理念の下にあるものと整理しています。
ミッション・パーパスは変えてよいか?
当然⽬的が変わった時には変えても良いですし、想いは変わらずとも時代に合う表現というものがあると思いますので、書き換えても問題はありません。
とはいえ、ミッションやパーパスというのはその企業の最上位⽬的であるため、滅多なことでは達成できるものではなく、⼀般的にはミッション・パーパスは「追い続けるもの」とし、それ以外のビジョンやバリューは時とともに書き変わることが多いです。
ビジョン(Vision)
ビジョンの重要性
なぜビジョンが重要かというと、どのような想い(ミッション・パーパス)があっても考えているだけでは意味がなく、その想いが実現したことによって誰かの役にたったり、社会が良くなったりすることが⼤切であるからです。
そこで、どのような状態になっていれば想いを実現したことになるのかを表したものがビジョンになります。
もっとも有名なビジョンは、ケネディ⼤統領がアポロ計画で世界ではじめて⼈類を⽉に送ると演説した以下の⼀⽂です。
“今後10年以内に⼈間を⽉に着陸させ、安全に地球に帰還させる”
なぜかというと、「⽉に着陸して旗を刺して返ってくる」という「絵=ビジョン」が思い浮かぶからです。思い描けないものは実現できませんので、素晴らしい表現だと思います。
これに共鳴し、NASAの清掃員の⽅がケネディ⼤統領に向けて「(私はただ掃除をしているのではなく)⼈類を⽉に送り出す⼿伝いをさせてもらっている」と話したのはあまりにも有名な逸話です。
そしてこのフレーズの背景として、アメリカがソ連に宇宙開発競争で劣後していたのを挽回するという⽬的がありました。それをここまで明確なビジョンを描いてプロジェクト化したことが計画成功につながったのではないでしょうか。

⺠間企業の具体例としては積⽔ハウスさんのこのビジョンがとても素敵です。
“「わが家」を世界⼀幸せな場所にする”
さらにその幸せを「健康」「つながり」「学び」の3つに因数分解し、これらを実現するために開発を⾏っていく、としてます。とても⼼に響く、⼈を導くビジョンではないでしょうか。
優れたビジョンの特徴
ビジョンの確認のために参考になるのはハーバードビジネススクール名誉教授であるジョン・P・コッター(John Paul Kotter)が提唱した「優れたビジョンの特徴」です。わかりやすくまとまっているので参考にどうぞ。
- ⽬に⾒える(将来がどのようになるのかがはっきりとイメージできる)
- 実現が待望される(皆がわくわくする)
- 実現可能である(現実的で、達成可能な⽬標になっている)
- ⽅向を⽰している(意思決定のガイドとなっている)
- 柔軟である(さまざまな選択を許容する柔軟性・弾⼒性を備えている)
ビジョンは常に書き換える。
ビジョンは常に書き換えるべきものです。なぜなら「実現すべき姿」であるためです。
アポロ計画の例では「10年以内に⽉に着陸する」ということが10年以内のビジョンであるため、達成したら次のビジョンを打ち⽴てることが重要になる、ということですね。
ミッション・パーパスを⽬的として、⽬標であるビジョンを達成し続けていくイメージです。常に新たに⽬標がある状態をつくり、達成していく会社をつくりたいですね。
バリュー
バリューの重要性
バリューが重要な理由は、打ち⽴てたビジョンをどのように実現していくかという価値観がなければ、組織⼒を発揮できないからです。
企業・組織・チームなどの組織体は、ざっくりいうと「⼀⼈でやるより⼤きなインパクトを出す」ために組成されます。⼀⼈でやるほうが⼤きなことができるなら、⼀⼈でやったほうが早いはずですから。
しかし、その組織体がバラバラの価値観で動いていたら、同じPLANをしてもDOが異なりますし、考え⽅が異なるためCHECKもACTIONもバラバラになってしまいます。つまり、会社がまわらなくなってしまうのです。
例えば企業成⻑の⼿段ひとつとっても、営業活動の強化をするのか、製品・商品・サービスの差別化や顧客セグメント・ターゲットの明確化をしていくのかなどで考え⽅が異なってきます。
あえてわかりやすい例を出すと、「売り込んででも伸ばす」のか「売れないならその理由を考えて改善する」のかで分かれるケースは多いです。前者は社員が疲弊し、離職率も⾼まってしまうのは⾔うまでもありません。
また、「どのような⼈と⼀緒に働けるか?」というのは個々⼈や会社の幸福、ウェルビーイングにとって極めて重要なファクターです。この⼈と働きたい、この⼈といると安⼼して働ける、そのような会社の幸福度が⾼いのはいうまでもありません。
同⼀の価値観の社員が増えてしまうことは多様性を犠牲にしないかという議論もありますが、これは多様性の⼟台になる話であり、多様性をさらに⾼めると考えています。
バリューの例としては、UZABASEさんの「7values」などが挙げられます。
私は経営コンサルティング業界に⻑くいますので、毎⽇寝れずにハイプレッシャーが続くなか仲間を助けられなかった後悔があったり、⼈を⾒捨てたり、他⼈や環境のせいにしたり、クライアントの圧⼒に負けて仲間の梯⼦を外したりするような様⼦を何度も⾒てきましたので、うえの画像でハイライトした ” In it together. No matter what ∕ 渦中の友を助ける ” というバリューは英⽂とともに物凄くグっときました。
このような価値観を持っている⼈を採⽤し、同じ価値観で仕事をしていければ、きっと良い会社になるだろうと思えますよね。
バリューは変わるのか?
バリューについては企業それぞれで、こうなりたいという想いから設定することもあれば、⼤きな事故や事件などの反省から設定することもあれば、過去の価値観が古すぎて時代にマッチしないから⾒直すこともあります。
以上から、バリューについては「今の経営ビジョンや経営戦略を実現するためにベストなものになっているか?」を定期的に問いながら⾒直していく、ということが環境変化の激しい今⽇においては有⽤ではないかと考えています。
企業理念・経営理念・事業理念・社是・綱領などとの違い
基本的には企業>経営>事業の順になっており、それぞれの最⼤の判断基準と捉えるのが良いです。
なぜなら、経営のために会社があるわけではなく、何かを実現するための会社のために、その会社を経営するという「⼿段」があり、経営するもののひとつとして事業があるためです。
経営理念は経営者が変わったい際に⽅針のような形で打ち出すケースもあります。
※もちろん明確な定義や決まりはなく、会社によっては経営理念を「企業理念」の位置づけで活⽤していることもあります。もちろんそれでも特に問題はありません。
例えば良い事業理念としてはインドのタタ・モーターズが発表した、nanoという当時世界⼀安価な⾃動⾞をつくった事業があります。
なぜ、ここまで⾼機能になっている⾃動⾞であえて最も廉価な⾃動⾞をつくることになったのかというと、当時の社⻑ラタン・タタ⽒が感じた、⾬の中にも関わらず、親が⼦どもをバイクに乗せて⾛っている姿を⾒て、もうこんな思いをさせたくない、という願いからスタートした事業だそうです。
結果はどうあれ、本当に素晴らしい考え⽅だと感動しました。社員がこの想いの実現のために奮起したのは想像に難くありません。⿃肌が⽴ちますよね。
また、「⾬の中、親が⼦どもと⾃転⾞に乗っている姿をなくす」という極めて分かりやすく明確なビジョンにもつながったはずです。
理念策定の実態。実は後から作られることも
ここまで理念について説明してきましたが、実際のところ理念は後から作られるケースもかなりあります。
私も含めて皆⼈間ですので、稼ぎたい、褒められたい、ただ現状から抜け出したいという想いから始まった会社や事業も多々あるわけです(そして、驚くほどにそのエネルギーは強く、むしろ創業期には活⽤すべきでもあります)。
ですので、今⽴派なものがなくても、会社が存在しているということは誰かや社会の役に⽴っているということですし、本当にやりたいこともやる気もないなら、転職したり会社を清算したりしているはずですので、⽇々の中に⼤切なことや埋もれていた想いがあるはずです。
いえ、これまで何百という事例を⾒てきて無いことはありませんでしたので、それは必ずあります。
だからこそ、現状を気にしすぎずに、まずは理念の策定や⾒直しからすべての経営改⾰はスタートさせるべきです。
まとめ
以上のように考えていくと、ミッション・パーパス、ビジョン、バリューは何ひとつ⽋けても成り⽴たない経営の根幹といえることがお分かりいただけると思います。
理念がなければ判断する際のよりどころがなく、⽬指す姿もわからず、組織も個々⼈がバラバラに動いてしまいます。つまり最も重要な仕事である判断のための「基準」がないのと同様といえます。
理念なしでは企業経営や企業改⾰はできませんので、まずはここからはじめましょう。これまで述べたように決まりはありません。
以下は花王さんの例ですが、表現はこれまで説明した内容と違いますがとても分かりやすくまとまっています(経営理念のことを「花王ウェイ」という表現にしています)。
余談ですが、理念は最近ではマインド・アイデンティティ(MI ー Mind Identity)と呼ばれることもあります。
MIとは企業の理念やビジョンを⽰したものであり、精神的な存在意義や⽬指す姿になりますのでほぼ同じ意味を指しています。
※具体的にはバリューをビヘイビア・アイデンティティ(BI ー Behavior identity)と呼び態度・⾏動の概念基準としていることもありますが、表現としてはまだ多くはありません。ちなみにMIとBIにVI(ビジュアル・アイデンティティ(VI ー Visual Identity)を加えたものを「CI(コーポレート・アイデンティティ)=企業として統⼀されたメッセージやイメージ」と呼びます。